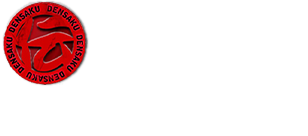販売商品
仙台で作られているだるまは、縁起のいいものがおなかのところに描かれており昔からみなに親しまれております。
堤人形は、ここ堤町の町の産業として町と人々に愛され育てられた人形です。
その堤町で製作をしているお店で、江戸時代には町の人ほとんどが製作に携っておりましたが時代と共に作り手は減り、
その中で、昭和初めまで製作していた宇津井家を始め他の数軒からここ「つつみのおひなっこや」では、
土型等約2,000個ほどを受け継ぎ製作しております。
(土型約1,700個は仙台市の有形文化財に指定されております。)
サイズ:横幅 20.5cmx高さ 24cmx奥行 19.5cm
【備考】
※お使いのモニターによっては、商品画像と若干の色合いの違いがございます。
※手作りの為、形や寸法などに若干の誤差がございます 。
¥3,960(税込)
◆コロンとした愛らしいサイズながら、青い縁取りと鼻筋の通った凛々しい顔立ちは、伊達なだるまの証。
◆手作業ならではのやさしい作りも人気の品、神棚から飾り棚や玄関、デスクの上などに飾っていただければ、その四方八方を見る大きな瞳で家内安全や無病息災を見守ってくれます。
◇東北・伊達藩の堤町から江戸期の古型(人形の型)を継ぐ数少ない伝統工房「つつみのおひなっこや」、そこで手作業で作られる「松川だるま」は、なかなかネットで出回らない希少な品です。
【仙台張子 松川だるま】
天保年間(1830~1844年)、伊達藩藩士・松川豊之進が創始したと伝えられている「仙台張子」。その仙台張子の代表格として作られている「青いだるま」が「松川だるま」です。
特徴は、青の色使いと、はじめから目が入っているところ。
顔周りの群青色は武士に愛されていた高貴な色で仙台の空や海を表現しており、黒々とした両方の瞳は、四方八方を見渡し、子供の健やかな成長を願うために作られてきました。
今でも仙台では、年の初めに縁起物の、このだるまを神棚などに祀り家を一年間見守ってもらう慣わしがあります。
材質 張子(仙台張子)、粘土
高さ 約10.0cm
幅・奥行 幅 約8.0cm
奥行 約8.0cm
重さ 約100g
¥990(税込)
◆お腹の大黒様がたくさんの福を連れてきてくれそうな宝尽くしの縁起物「松川だるま」。
顔まわりには海老熨斗(のし)を表した水玉模様。胴体脇には“寿”の字を書きくずした梅の木に花が咲きほこります。
◆伝統工芸品としても人気の品、神棚から飾り棚、リビングや玄関に飾れば、その四方八方を見る大きな瞳で家内安全や無病息災を見守ってくれます。
◇東北・伊達藩の堤町から江戸期の古型(人形の型)を継ぐ数少ない伝統工房「つつみのおひなっこや」、そこで手作業で作られる「松川だるま」は、なかなかネットで出回らない希少な品です。
【仙台張子 松川だるま】
天保年間(1830〜1844年)、伊達藩藩士・松川豊之進が創始したと伝えられている「仙台張子」。その仙台張子の代表格として作られている「青いだるま」が「松川だるま」です。
その特徴は、青の色使いと、はじめから目が入っているところ。
顔周りの群青色は武士に愛されていた高貴な色で仙台の空や海を表現しており、黒々とした両方の瞳は、四方八方を見渡し、子供の健やかな成長を願うために作られてきました。
今でも仙台では、年の初めに縁起のいい、このだるまを神棚などに祀り家を一年間見守ってもらう慣わしがあります。
材質 張子(仙台張子)、粘土
高さ 約18.0cm
幅・奥行 幅 約14.0cm
奥行 約14.0cm
重さ 約355g
¥2,420(税込)